はじめに
この記事では、私がジムに着いてから登るまでの間に行っているストレッチ方法について記載していこうと思う。ちなみに、この内容をまともにやり始めてからは一度も怪我をしたことがない。今まで何度か書こうと思っていたが、科学的な有意性を調べて行っているわけではなく、かなり経験的なストレッチ方法となってしまうため、後回しにしていた。
一応、筆者のスポーツ経験(サッカー、陸上、水泳、登山、空手、クライミング)で学んだことや、Youtubeでヨガや肩甲骨可動域拡大動画を見ながら実践して、効果ありそうだなと思ったこと、そしてCLIMBERS等のクライミング雑誌で取り上げられた内容を盛りこんで、短時間に落とし込んだものとなっている。大体10分前後で終わる。なんかストレッチ足りない気がするんだよなぁと思う方が一部でも参考にしてくださったら嬉しいです。
※参考画像はGoogle画像検索から引用しました。
股関節可動域拡大&怪我防止編
書いてある順番で行っていくと、ストレッチ時のストレスが少ないです。
足折り畳み

陸上やサッカー等でよくある汎用的ストレッチ方法の1つ。太ももの表筋を伸ばす。そこまで痛い姿勢ではないので、ストレッチの導入としては最適。余力のある人は、たたんだまま後ろに寝たり、両足同時にやってもOK。
① 左足を後ろに折りたたむ
② 体軸を左右に回転させる(各5sくらい)。
③ 右足の場合も同様に行う。
足三角交差

これまた陸上やサッカー等でよくある汎用的ストレッチ方法の1つ。痛くなく、普段固まっている部位が伸びている感覚も実感しやすいので、ストレッチ序盤に最適。
① 右足を伸ばし、左足をその上から交差する。
② 右手を、交差した左足の左側に置いて支点を作る。
③ 後方に置いた左手を軸に、体軸を左後ろにひねる
(きついところで、5~10sくらい固定)
④ ①に戻って、左足を伸ばしたverも同様に行う。
半開脚メドレー

開脚の半分ver。開脚ストレッチの効果にプラスして、ヨガの動きも取り入れている。太ももの裏筋を伸ばし、股関節付近の可動域も大きくする効果がある。
【ウォームアップ】
① 左足をなるべく真横に伸ばし、右足は股関節側に折りたたむ。
② 左足の踵を地面につけた状態で、足先だけを正面側に90度傾けて元に戻す動作を繰り返す。
② 右手と左手を左足に付けることを意識しながら体を伸ばす(5~10sくらい)。

【太もも裏側のストレッチ】
③ 体勢を少し変え、折りたたんだ右足の上に体重が乗るような姿勢に移行する。
④ 右太ももの筋が伸びていると思った姿勢でキープする(5~10s程度)。
【股関節のストレッチ】
⑤ ④の状態から最初の半開脚の状態に戻す。
⑥ 左足の踵を地面につけた状態で、足全体を正面側に90度傾けて元に戻す動作を繰り返す(5~10回)。
【半開脚前屈】
⑦ 半開脚のまま、普通の開脚と同じように正面に体を徐々に倒して、キツイところで5~10sキープする。
⑧ ①に戻って、右足を伸ばしたverも同様に行う。
開脚メドレー

一般的な開脚に加え、空手やバレエで習う股割ストレッチも追加したもの。ストレッチを楽にするために、多少、股関節運動も加えている。
【ウォームアップ】
① 両足を180度に近づくように両側に広げる。
② 股関節を意識して足先を正面に90度程度前後させる。(半開脚の②の両足ver.)
③ 右手と左手を片方の足に付けるように体軸を伸ばす。
④ 反対側の足も同様に行う。
【開脚前屈】
⑤ まずは、体の硬さをほぐすために、股関節を意識して体を前後にゆっくり揺らす。
(前:少し体を沈み込ませるイメージ、後:少し体を反るイメージ)
⑥ 体を前面に徐々に倒していく。
⑦ キツイ姿勢で5~10sキープする。
【股割】
⑧ 体勢を変え、股割に移る。
⑨ 左→正面→右の順に各姿勢5~10s程度キープする。



閉脚

これもよくある閉脚ストレッチを少しアレンジしたもの。
① 両足を畳んで体の正面で足裏同士をくっつける。このときくっつける位置をなるべく股関節に近づけること。
② 体を前方に倒してきついところで5~10sキープ。このとき、背中を丸めずに背筋を伸ばした状態で倒すこと。
③ 折りたたんだ左足の上に左肘を置き、左太ももがあがらないように抑え込んだうえで右掌で右足を押す(5~10回)。
④ ③の逆も同様に。
腕正面・背面交差


どのスポーツでも絶対やったことのある動き。詳細は割愛する。キツイところで5~10s程度キープする。
手首運動

これは手首が弱い人はやったほうがいいと思う。不安定な体勢からのゴールランジ時の手首の振られ(回転)にある程度耐えられるようになるが、シチュエーションが限定的なため、マストではない。
① 胡坐をかく
② 手首を180度反転させ、地面につけて5~10sキープ。
③ 手首を225度反転させ、地面につけて5~10sキープ。
④ 手首を270度反転させ、地面につけて5~10sキープ。
アキレス腱

あまりクライミングには効果はないが、念のため。よく見るので勘違いしている人が多いと思うのですが、アキレス腱を伸ばしたまま前後に揺らすのはNG。伸びてるなと思ったところでしっかり踵を地面につけ、5~10sキープしましょう。
肩甲骨可動域拡大編
ヨガの動き、CLIMBERSに載っていた楢崎智亜のストレッチ、そして、昔 Youtubeで見つけた肩甲骨可動域拡大ストレッチ動画の動きを組み合わせたもの。URLはもう忘れてしまいましたが、「立甲」とか「肩甲骨剥がし」等で検索すると多くの動画がヒットするので、文字だけでは分からなかったら参考にしてみるのもいいかもしれません(人によってやり方はかなり違いますが)。
Orzの姿勢・導入編

結構気持ちよくて眠たくなる。可動域ストレッチ序盤にオススメ。ヨガの動きとして正式な呼び名があった気がする。
① orzの姿勢になる。
② __orzのように、額を地面につけながら腕と腰を前に伸ばしていく。
③ 肩甲骨付近が伸びたなと思ったら、そのままほんの少し左右に体を揺らしながら5~10sキープ。
Orzの姿勢・可動編

ここからが肩甲骨可動域拡大ストレッチ。動きが若干卑猥なため、ストレッチスペースの隅っこで行おう。
【前後】
① orzの姿勢で両手両足をやや狭めの逆八の字に。
② 肩甲骨付近を伸ばすイメージを持ちながら、両手と膝の地面接地の位置は変えずに体を前後に伸ばす。
(後ろで溜めを作り、少し勢いをつけて前に伸ばす)
③ この時、一番前後に伸び切るところで1s程度キープしながら10往復くらい繰り返す。
【左右】
④ 次に、前方に伸びきるところで左右に体を揺らす。
肩甲骨を意識しながらお尻を揺らすイメージ。これも10往復くらい。
Orzの姿勢・ウォームアップ編

楢崎智亜がCLIMBERSで紹介していたストレッチの易しめver。しかし、要は一本腕立て伏せの簡易版なので、筋肉と手首への負担が少し大きいです。疲れてしまう方は無理せずに5回以下にしておきましょう。
① 膝立ちのorz姿勢で片腕を背中側につけ、もう一つの腕だけで体を支える。
② 地面に設置している支点の腕を軽く上下に屈伸させ、肩甲骨を動かす(5~10回)。
③ 逆の腕でも同様に。
さいごに
「クライミングを長く続け、上達していくには怪我をしないことが第一」ですので、もし気に入ったストレッチ方法があれば、自身のストレッチメニューに取り入れてみてください。また、他にもおすすめのストレッチ方法を知っている方がいれば、コメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。また、今回紹介したストレッチはあくまで普段家で柔軟を行わない方を対象とした静的ストレッチの一種であり、日常的に家で柔軟を行っている方は速く筋肉を温めることのできる動的ストレッチの方を推奨いたします。



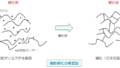
コメント